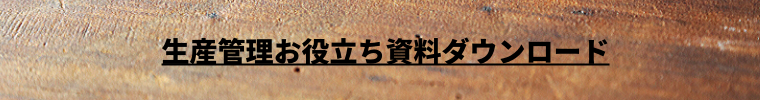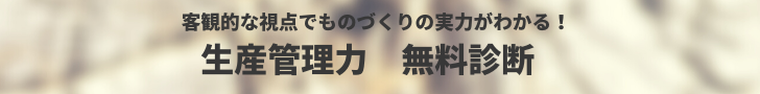製造業における「SoR」「 SoE」とは何か?
●SoR SoEとは何か?
三文字略語が多いIT業界ですが、またもやあまり馴染みがない文字が・・・登場しました。
SoR(System of Record)は、「記録するシステム」と約せます。
判りにくいですね。
一般的には、生産管理システムなどの業務システムを指します。
受注を記録し、生産指示、実績を記録する。そして出荷や売上を記録する。まさに「記録するシステム」です。
このSoRは単体ではあまり説明がされておらず、製造業であれば、 Iotやインダストリー4.0との関わりから、SoEという略語と対で説明されている場合が多いようです。
SoE(Systems of Engagement)は、「約束や絆のシステム」と訳されたり、「人、モノ、コトに対して積極的に関与するシステム」と説明されています。
これも何だか判りにくいですよね。
2011年に米国で発表された記事から広まったこのSoEは、ものづくり現場であれば、顧客や仕入先、外注先などの関係性(絆)を強化して仕事に活かす事を意味します。
絆ですから、片方向ではなく、両方向の繋がりをより強めるためのシステムです。
ただ、その手段は「ITの力」を活用する事です。
例えば、製造メーカーであれば、SNSなどから機器の評価や新たなアイデアを収集し、開発部門と積極的に関係性を深め、新製品開発に活かすなどがあげられます。
SoEは、このような新たな製品、サービス、または経営判断に利用できる情報を積極的に関与するITシステムといえます。ITの進展により、これらを実現するSoEが注目されています。
しかし、これまでのSoRである生産管理システムでは、絆のための情報は扱っていなかったのでしょうか?
得意先との関係強化のため、内示情報や需要予測を適宜確認し、先行手配や短納期生産を行う事は日本の製造業の得意な事です。
そういう意味では、「我が社は絆のために積極的に関与してきたよ」と思われるかもしれません。
ただ、ITを積極的に活用している場合は少ないのではないでしょうか?
●SoR、SoEを考える上で必要な「定形データ」と「非定形データ」
SoEは、SoRで扱うデータは、「定型データ」「事実」というより「非定型データ」 「情報」というイメージです。
情報といっても「ITの力」を活用するわけですから、システムの内部はデータです。つまり、SoRとSoEでは設計思想(アーキテクチャ)に違いがあるといえます。
クラウドやビッグデータの発展に伴い、Iotの範囲も拡大し、これら大量のデータをリアルタイムに分析できるようになってきています。
データを分析し情報に変える技術が進展してきた・・と考えると判りやすいでしょう。
SoRである生産管理システムを利用している製造業においても、アーキ テクチャが違うSoEとのデータ連携や情報連携ができた企業は、他社と大きく差別化を図れそうです。
今後、これらの事例に注視し、自社で可能な「関係性強化」を模索してはどうでしょうか。