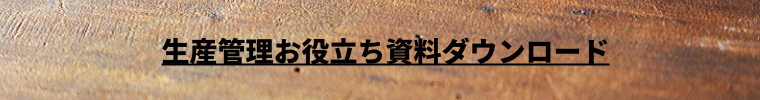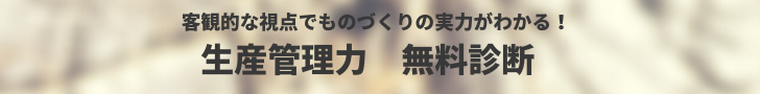取引先マスターチェックしましたか?令和6年11月1日改正 下請中小企業振興法の振興基準変更
----------------------------------
取引先マスターチェックしましたか?
令和6年11月1日改正
下請中小企業振興法の振興基準変更
----------------------------------
振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者の取るべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。
ひらたく言えば、下請法順守の行政指導の基準を定めたものです。
令和6年11月1日以降、下請法上の運用が変更され、業種を問わず、60日を超えるサイトの約束手形や電子記録債権の交付、ファクタリング等の一括決済方式による支払は、下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれのあるものとして、行政指導の対象となります。
手形は、特定の期日に決められた金額を支払うことを約束する有価証券です。
「江戸時代から商習慣として存在し、明治期以降に制度や法の整備が進められ、支払い手段として確立・普及し、日本、韓国、中国など世界でも限られた地域でしか見られない商習慣だそうです」(中小企業庁 ミラサポ)
「長い期間現金支払いを猶予されることで、事実上、下請企業に資金繰りを負担させるという弊害を軽減すると同時に、手形が多用されることで、国際的に見て長い傾向にある日本の支払いまでの期間を短縮して国際的観点から日本のビジネス環境を魅力あるものに整備していくという」意図もある」(同上)
これらの背景から振興基準を定め、定着を図る目的があります。
基準を順守していくためには、発注システムなどの取引先マスターが正しく設定され、運用されているかのチェックが必要です。
多くの製造業では、自社が親事業者である場合に加え下請事業者の場合があります。
そのため、上記のマスターチェックでは、支払いと入金のそれぞれの条件を確認しておく必要があります。
つまり、モノとしてのサプライチェーンと同期し、支払い手段としてのサプライチェーンの適正化をチェックする事になります。
ここで、下請代金支払遅延等防止法(下請法)について少し復習しておきましょう。
下請法は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律です。
製造業の場合、製造委託や修理委託において、親事業者と下請事業者の資本金の大小で下請取引かを判断します。
親事業者の資本金が1千万円超から3億円以下では、1千万円以下の下請事業者(委託先)への依頼は、下請取引に該当します。
資本金が3億円超の場合においても、資本金3億円以下の子会社を通じて委託取引を行っている場合に、親会社-子会社の支配関係や関係事業者間の取引実態が一定の要件を共に満たせば、その子会社は親事業者とみなされて下請法の適用を受けます。
これはトンネル会社規制といわれています。
また、試作品等の委託において、商品化することを前提にした製造委託も(類型1として)下請取引に該当します。
そのため、製造や購買部門以外に設計部門なども関係してきますので注意が必要です。
当然、規格品や汎用的な部材購入等で、役務が生じない取引は下請取引に該当しません。
下請法では、これら「義務」と「禁止事項」が定められていますので、マスターのチェックと同時にその内容についても再度確認しておく方が良いと思います。
中小企業庁では、長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、支払条件の改善を中小企業の取引適正化の重点課題の1つとし、
業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、手形等による支払期間の短縮を推進しています。
今回の要請文には、手形等のサイト短縮の要請以外にも、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めることについても記されています。
昨今の人手不足や物価高での取引価格上昇の転嫁に関しても、下請法の禁止事項である「買いたたき」に該当する可能性があるため留意が必要です。
以下が条文に記載されています。
「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、
従来どおりに取引価格を据え置くこと」
つまり、暗黙の了解ではダメで、交渉の場を設け協議をしなさいという事です。
「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等が上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面等で
下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」
つまり、口約束ではダメで、要請に応じ、なぜ取引価格を据え置くのかを書面で残しなさいという事です。
製造業全体のサプライチェーンを維持するためにも、適切な取引を行っていくべきかと思います。